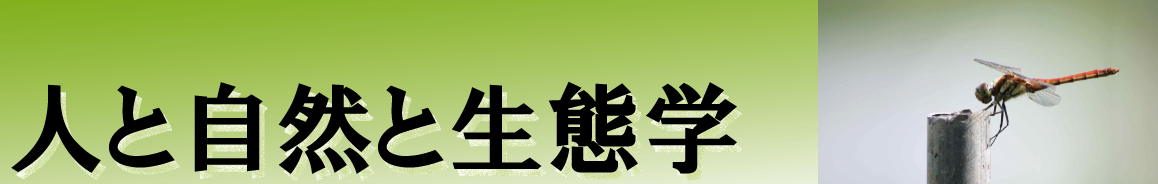■はじめに

第2回に参加してくださった皆さんから,「身近な生物を題材にした講座を」という意見を多くいただきました。
そこで,市民講座の第2回では「花」にフォーカスをあてて,私たちの当初の「ねらい」である生き物の間の様々な関係,例えば競争(きょうそう),共生(きょうせい),寄生(きせい),あるいは「捕食・被食(ほしょく・ひしょく)関係などの生物間相互作用(せいぶつかんそうごさよう)にも興味を持っていただけるようなプログラムを企画いたしました。
「花」そのものの話題や花と虫との関係をお楽しみください。
(写真: ノリウツギ)
■虫をあてにしない花たち
平塚 明 ( ひらつか あきら )[岩手県立大学総合政策学部]

花をつけても開かない植物がいます。閉鎖花植物。虫も風も頼りにせず、閉じたつぼみの中で自家受粉をする花たちです。土の中に花をつけるものもいます。
一方で、こうした植物たちは普通に咲き、虫に助けられて受粉する花も用意しています。つくられ方のちがうタネは形も大きさも、その後の行き先も異なります。二つのタイプの花とタネを使い分けている植物の生活をご紹介します。そして、性と花が進化した理由についても少しだけ考えてみます。
(写真: フタリシズカ)
■サクラソウのタネが実るためには
本城 正憲 ( ほんじょう まさのり )[東北農業研究センター]

サクラソウは北海道から九州、アジア大陸北東部に分布する多年生草本です。岩手山麓には数多く生えており、宮沢賢治の作品にも登場します。しかし、近年では全国的に減少し、岩手でも昔に比べ少なくなったようです。サクラソウがこれからも生き延びていくためには、タネを作ることが重要です。
では、サクラソウのタネが実るためにはどういったことが必要なのでしょうか? 本講演では、サクラソウの種子生産を通して、生き物のつながりについてみていきます。
(写真: サクラソウ)
■湿原の花と虫たちのゆるやかな関係
鈴木 まほろ ( すずき まほろ )[岩手県立博物館]

町には様々な食堂があります。すぐに食べられるファストフード店、高級フランス料理店、家族や仲間と賑やかに過ごすレストラン、知る人ぞ知る隠れ家カフェも・・・それぞれ店構えに工夫があり、お店に合った客を誘っています。
花も同じです。野外の花には様々な虫が訪れ、蜜や花粉を食べて去って行きます。花は、虫のレストランなのです。花の色や形、サイズが違えば、訪れるお客も変わります。
今回のお話では、湿原を舞台として、どんな花にどんなお客さんが来るのか、そして、なぜそんな風になっているのかを、少しだけのぞいてみたいと思います。
(写真: 春子谷地)